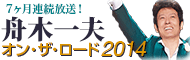クリックで今日のランキングが見れます
ご同輩の皆様方には、読んでいただくと「あぁそうだった」「そんな事もあった」と懐かしく読んでいただける本であろう。さすらいもご多分に漏れず、昭和の時代の話が大好きで、いつもの事ながら同世代の方と話をしていると、昔の懐かしい話に没頭してしまう。例えばがん治療薬の「丸山ワクチン」とか、貧乏旅行でリュックを担いだ「カニ族」とか、「力道山」の話しとか。(笑)殆ど知っている事ばかりですが、改めて読むと当時を思い出します。さてこの本の中ににも、舟木さんの話題が書かれています。舟木ファンの皆さんには、当然ご存じの事なのですが、本に書かれた部分をちょっとご紹介しておきましょう。それは、いろいろなジャンル分けの中の「音楽・芸能」と言うところの冒頭に書かれています。舟木一夫にまつわる2つの秘密
♪赤い夕陽が 校舎を染めて・・・ と一人のツメ襟姿の青年が学園賛歌を歌いました。♪ぼくらフォークダンスの手をとれば 甘く匂うよ 黒髪が・・・と続く歌詞に、青春の恋のときめきを感じたものでした。昭和38(1963)年「高校三年生」でデビューした舟木一夫は、面長で清潔感のある雰囲気がうけて、たちまちお茶の間のアイドルになりました。
舟木一夫の曲は、映画化もされています。「高校三年生」は、倉石功と姿美千子が主演、舟木はこの映画に二枚目半的な役でゲスト出演しています。
「学園広場」では松原智恵子と組み主演の座へ、その後、本間千代子とのコンビで「君たちがいて僕がいた」、和泉雅子とのコンビで「北国の街」「高原のお嬢さん」「絶唱」に出演しました。
中でも「野菊の墓」の現代版とも言うべき「絶唱」は、多くの人の涙を誘いました。舟木映画の原作は、のちにポルノ作家に転進した富島健夫によるものがほとんどで、当時の富島は、ジュニア小説家として頑張っていたのです。
ところで、舟木一夫と言う芸名は最初は橋幸夫に贈られるはずのものでした。舟木と橋は2人とも作曲家の遠藤実に師事していて、遠藤は先輩である橋に以前から温めていた芸名「舟木一夫」をプレゼントするつもりでした。ところが、橋が作曲家吉田正の門下に入ってしまったので、後輩の舟木にこの名前が贈られたというわけです。まぁさすらい的には、幾つか異論がありますね。(笑)舟木映画のほとんどが富島健夫原作のように書かれていますが、「高校三年生」と「君たちがいて僕がいた」「北国の街」の三作品だけですから、ほとんどと言うのは、間違いでしょう。「高校三年生」の原作は「明日への握手」。「北国の街」の原作は「雪の記憶」「君たちがいて僕がいた」は同名で、月刊明星に連載されていました。「野菊の墓」の現代版と言うのも当てはまるのかな?確かに原作の伊藤左千夫が発表したのが明治時代で、絶唱は昭和の戦後ですから、50年ほど開きがありますが、それからさらに50年近く経つわけですから、現代版と言う言葉はピンときませんね。青春歌謡の御三家プラス三田明
歌は世につれ 世は歌につれ という言葉がありますが、団塊の世代の誰もが、心に残る愛唱歌を一つや二つ持っているでしょう。日本の歌謡史をたどれば、団塊の世代が生まれる前後に、美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみの「三人娘」が相次いでデビューし、その後、昭和33年頃には、山下敬二郎、ミッキー・カーチス、平尾昌晃などが活躍した、ロカビリーブームの到来となります。そして、青春期を迎えた昭和30年代の後半から40年代前半の役10年間は、青春歌謡の全盛期でした。
この青春歌謡の時代に活躍したのが、橋幸夫(昭和35年「潮来笠」でデビュー)、舟木一夫(昭和38年「高校三年生」でデビュー)、西郷輝彦(昭和39年「君だけを」でデビュー)などで、この三人はのちに御三家と呼ばれました。
売り出すレコードは次々にヒットし、「ロッテ歌のアルバム」などテレビ歌番組にも引っ張りだこで、歌に合わせて制作された映画にも出演してヒットを飛ばすなど、まさにビックアイドルでした。
団塊世代の青春時代は、男女の交際も今ほどフランクではなく、こうした思春期の感情を青春歌謡にぶつけていたような気がします。たとえば、「高校三年生」がヒットした年に中学三年生だった生徒は、この歌の「高校三年生」の部分を「中学三年生」と言い替えて歌ったものです。
この御三家のあと三田明が「美しい十代」でデビューいてヒットしました。
この歌を団塊世代は「美しい50代、あぁ60代」などと言い替えて歌っているようです。三田さんが「御三家」のあとではない事はお分かりですよね。(笑)まぁこんな感じでこの本は書かれています。あまり詳しい本ではありませんが、昔を懐かしむという部分では、さらさらと読める本です。本の冒頭に「居酒屋のコミュニケーションツールとして」と書かれています。確かにこの本を持って、同世代とのお喋りするには良い本ですね。